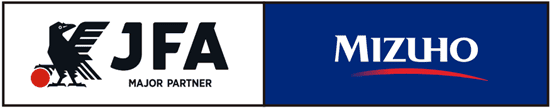――JFAインクルーシブプログラムについて、立ち上げたきっかけなどを教えてください。
岩田 2021年3月の日本代表戦の際、スタジアム内専用ラジオで生放送を聞きながら観戦できる「実況解説シート」をトライアルで販売したのが始まりです。それまで障がいのある方向けの席種は車椅子席のみでしたが、障がいの特性は人によって違うため、困りごとや配慮の仕方も異なります。私はロービジョンで視覚障がいがあるのですが、2018年にイングランド・プレミアリーグの試合で、スタジアム内で実況を聞きながら応援を楽しむ経験をしました。日本でも視覚障がいのある方が家族や友人とスタジアムで日常的に試合観戦を楽しめるサービスが提供できればと提案し、取り組みがスタートしました。
――プログラムを進める上で重要視したポイントや検討してきたことは何でしょうか。
岩田 「障がいがあっても、一般のファン・サポーターと共にスタジアムでサッカー観戦を楽しんでもらおう」というのが目的です。Diversity(ダイバーシティ/多様性)、Equity(エクイティ/公平性)、Inclusion(インクルージョン/包括性、受容性)の頭文字を取った「DEI」という言葉がありますが、それをスタジアムでの試合観戦に例えてみます。ダイバーシティは、スタジアムに集まる観客一人一人が異なる背景や特性を持っている状態を指します。例えば、年齢や性別、国籍、障がいの有無など、多様な人々が同じ試合を観戦している状況です。
エクイティは、全ての観客が試合を公平に楽しめるよう、それぞれの背景やニーズに応じたサポート・配慮が提供されることを意味します。例えば、車椅子利用者や知的・発達障がいのある方のための専用観戦エリア、移動ルートの設置、視覚に障がいのある方への音声サービスの提供など、個々の状況に応じた支援が行われることです。最後にインクルージョンは、多様な観客が互いの違いを尊重し、誰もが安心して試合を楽しめる環境が整えられている状態のことです。具体的には、全ての観客が一体となってチームを応援し、誰もが疎外感を抱くことなく、共にサッカーの魅力を共有できる雰囲気の醸成が考えられます。
これらを念頭に置いて、試行錯誤を繰り返してきました。私ももともと熱狂的な日本代表サポーターでしたし、自分の経験に基づくいろいろな事例や福祉の制度などを踏まえながら、実際の声やニーズにも耳を傾けてスタジアム内での課題を整理し、またJFA競技運営部の担当者らと話し合い、改善を図ってきました。
――現在はどういったことに取り組んでいますか。
岩田 観戦エリアとしては、視覚障がい者席、知的・発達障がい者席、そして従来販売していた車椅子席の3席種があります。そのほか、試合前に審判員と選手が入場する際、共にピッチに入場いただく体験「プレマッチセレモニー」を実施したり、それに関連してスタジアムで啓発動画を放映したりして、障がいのある・なしにかかわらず一緒に日本代表を応援するという機運を高め、同時に社会での行動変容を促すきっかけづくりなども行っています。そして2024年3月からはみずほさんに協賛していただき、「JFAインクルーシブプログラム supported by MIZUHO」として実施しています。
――あらためて協賛に至った背景や思いなどをお聞かせください。
堀 みずほでは、全ての社員が自分らしく輝き、関わる全ての人や社会に新たな価値を生み出すために、「DEI」を会社全体で推進しています。また、みずほとして「DEIコミットメント」を掲げているのですが、JFAインクルーシブプログラムとの親和性は非常に高いと感じ、この素晴らしい取り組みをサポートしながら、さらに良いものを提供できればと考えました。みずほが長く協賛しているサッカーを通して、「DEI」の取り組みを実現できることはうれしいですね。
岩田 ありがとうございます。プログラムに共感し応援いただけると聞いたときはとてもうれしかったです。私は目が見えにくくなったとき、スタジアムに行くことを最初は諦めていました。しかし、友人の粘り強い誘いでスタジアムに行き、スタジアムでの体験が、サッカーが勇気を与えてくれました。このプログラムを通じて初めてサッカー観戦に出掛けたり、日常で小さな目標を持ったりということがあると思います。継続していくことで、より多くの人に興味・関心を持ってもらえればと考えています。
――2024年3月以降、協力体制を築きながらどのような取り組みをされてきたのでしょうか。
岩田 本格的に取り組みをスタートしたのは、2024年6月のFIFAワールドカップ26アジア2次予選のSAMURAI BLUE(日本代表)の試合でしたよね。
堀 エディオンピースウイング広島(広島県)で行われた試合ですね。この時に初めて、プレマッチセレモニーの参加者をみずほで募集させていただきました。多くの応募があり、その中から車椅子を日常的に使用されている方1名、視覚障がいの方1名に参加いただきました。セレモニー後は「BLUE DREAM SEAT」と命名した席で観戦していただき、視覚障がいの方は小さなお子さんだったのですが、音声配信を聞きながら試合を楽しまれていて、笑顔がとても印象的でした。
岩田 プレマッチセレモニーへの参加は、FIFAワールドカップカタール2022で選手が障がいのある方と一緒に入場しているのを参考に、JFAでも2023年から導入しました。われわれとしては、障がいのある方、一般の方も含めて意識を変えていくことを目指していますので、移動に困難を伴う方が審判員や選手と一緒に歩くことに意味があると考えています。
プレマッチセレモニーの前には、試合前のウォーミングアップに向かう選手とハイタッチができたり、プレマッチセレモニー時は審判員や選手と一緒に整列したりするなど、何物にも代えがたい貴重な経験を積むことができます。
――プレマッチセレモニーの際は、来場者の中から介助者を選んでいます。
岩田 一般の皆さんへの啓発も兼ねて、スタジアムに来場されたファン・サポーターから当日募集し、介助者として一緒に歩いてもらっています。スタジアムに来れば、日本代表を応援する気持ちはみんな同じですし、共にピッチに立つことで同じ目線を共有できるのではないかと。こうした経験をきっかけに、障がいのある方への認識が変わり、日常生活でも支え合えるようになると信じています。
堀 車椅子を押すのが初めての方もいますので、自己紹介から始まり、さまざまなレクチャーを受け、実際にコミュニケーションを取りながら介助しています。限られた時間の中で理解して、自然に行動できるところは本当に素晴らしいですし、実際に何かを感じるきっかけにもなるのかなと思います。
――年間を通してどのような形で進めていますか。
岩田 スタジアムなどの施設や試合によって、サポートの仕方が異なります。今言った6月のSAMURAI BLUEの試合、それからなでしこジャパン(日本女子代表)の2試合、7月に石川県で行われた「MS&ADカップ2024~能登半島地震復興支援マッチ がんばろう能登~」や10月の東京都・国立競技場での「MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024」では特に連携して多くのサービスを提供しました。
堀 スタジアムによってボランティア募集の有無も変わってきます。社員のボランティアを募集したのは、広島の試合と国立競技場での試合になります。
――実際にボランティアスタッフはどのような関わりをしているのでしょうか。
堀 広島の試合では、社内で募集をかけてボランティアスタッフが数人参加しました。当日は、「BLUE DREAM SEAT」の受付からご案内、そしてサポートとボランティア業務は幅広いものでした。ボランティアは初めての社員が多く、どう関わればいいのか、どういったサポートが必要なのかなど、相談しながら対応していきました。現場には岩田さんもいらっしゃったので心強かったですね。
岩田 これまでもそうですが、皆さんは経験がなく、介助や付き添い方などどうすればいいのか分からない。視覚障がいの方と一緒に歩くときはこうすべき、車椅子はいきなり押さないなど、いろいろあるわけです。代表的な方法は事前に専門団体の方にレクチャーいただいてから、来場される方への対応を行っています。
ただ先ほどもお伝えしたように、障がいの特性は異なりますし、スタジアムによって案内ゲートから座席、トイレ、売店の位置などいろいろとハードルがあります。できる限りスタジアム内で安心して過ごしていただけるようにするのが、介助者であるボランティアの役割です。実際の現場では、私もサポートしながら、ボランティアスタッフの皆さんが積極的に取り組んでいただけた印象です。
――ボランティアを経験した方々からはどういった声が聞かれますか。
堀 参加した社員からは「今まで気付けなかったことに気付けるようになった」「この気付きをボランティアだけでなく、職場でも共有し、会社の良いカルチャーにしていきたい」といった心強い言葉をもらっています。良いものを持ち帰ってもらうことができたと感じていますし、今後もこうした機会を増やしていきたいと思っています。
岩田 余談ですが、みずほさんのボランティアスタッフの方に私がロービジョンフットサルの日本代表選手だと伝えたところ、私のクラブチームの地域カップ戦の応援に来てくれました。スポーツを応援するのが元々好きな、とても熱い方でした(笑)。
堀 その社員からも応援に行ったという話を聞きました。日本代表戦でボランティアを経験した後、いろいろなスポーツでボランティアを続けているそうです。車椅子の方のアテンドの際に、初めは押しながら「車椅子の方が通ります、すみません」と謝っていたところ、「通っているだけで、何も悪いことはしていないから『すみません』と言う必要はない」と岩田さんに教えてもらったことなども、日常の生活や職場でしっかり実践してもらっています。
――これまでの取り組みの中で印象に残っていることは?
堀 広島での試合のプレマッチセレモニーには、病気で倒れて以来、体のまひと記憶障がいが残っている方が参加されました。ご家族から「病気で倒れてから20年くらい、本当に大変なことが多かったけれど、生きていればこんなにも素晴らしい体験ができるんだと思った。一生の宝物になったので、ぜひこのプログラムを続けて、たくさんの人に体験してもらいたい」と言っていただいたのは特に印象に残っています。
また、石川でのセレモニーに参加された方は、応募した後に持病が悪化してしまい、当選の連絡をした時は入院されていたんですよ。「すごく体調が悪いのですが、ぜひやらせてください」とおっしゃって、実際にその後は一気に快方に向かわれた。当日は遠方から石川まで来て、ものすごく元気に、笑顔で参加していただけて、“サッカーが大きな力になったんだ“と確信しました。その方は10月の試合にも観戦に来ていましたし、こういったつながりは大切にしていきたいと思いました。
――今後プログラムをどう発展させていきたいとお考えでしょうか。
岩田 JFAでは2024年、多様な人がサッカーにアクセスできる機会と選択肢を届ける「アクセス・フォー・オール宣言」を出しました。私自身、26歳で視覚障がい者になった時、最初は「夢すら持てない」と思いましたが、サッカーから生きる力をもらい、「夢を持っていいんだ」と夢への勇気が湧き、前に進みたいと思えるようになりました。そういった機会を多くの方に届けたいですし、私も難病のため、特に病弱でスタジアムに来ることが難しい方たちへのアプローチも考えていければと思っています。そのためにも、みずほさんとのインクルーシブの取り組みをさらに充実させていきたいと思います。
堀 「インクルーシブプログラムに参加して良かった」「スタジアムに行くきっかけになった」という方が少しでも増えればうれしいですし、それが私たちのミッションだと思っています。また、障がいのある当事者や関わる方だけでなく、スタジアムに訪れる方を含め、たくさんの方にこのプログラムを知ってもらいたいですね。私たちみずほとしても、社内で活動の認知を広げ、ボランティアに参加して気付きを得て、それをまた社内での取り組みやお客さま対応などの業務にもつなげるサイクルを築いていきたいと思います。
今後も、みずほはJFAやこの取り組みに賛同し参加いただける皆さんと共に、サッカー、そしてインクルーシブプログラムを通じて、共生社会の実現を後押ししていければと思います。